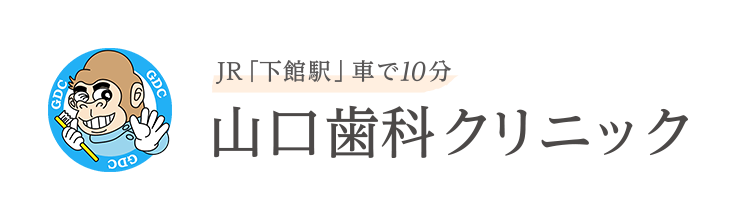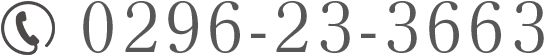2022年01月6日
歯がしみる!何が原因? 〜お口豆知識
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 雪の1日となりました。雪国なら当たり前のスタッドレスタイヤも平野部の雪が少ないような地方では全てのクルマが履いているわけではないようです。 坂道とかでノーマルタイヤで […]


2022年01月6日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 雪の1日となりました。雪国なら当たり前のスタッドレスタイヤも平野部の雪が少ないような地方では全てのクルマが履いているわけではないようです。 坂道とかでノーマルタイヤで […]

2021年12月23日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 年末もおし迫って今年もあと何日かですね。慌ただしくなるのが年末らしいと言えばそうなのですが、慌ただしくなっても自分のペースは守っていきたいですね。 人のペースのまま動 […]

2021年12月16日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 新型コロナも変異を繰り返して今ではオミクロン株のものが世界中で広がりつつあるようです。 感染症防止の基本はうがい手洗い、密にならない、大声で話さない、等は変わらないで […]

2021年12月9日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 寒いからか我が家に野良猫が何匹かやってくるようになりました。雨風しのげるところがあるから居心地がいいのかくつろいでいる様子をよく目にします。ただ私が近づくと逃げてしま […]

2021年12月1日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 今朝方の雨はすごかったですね。雷が鳴り風が強く吹いて嵐のようでした。 天気が崩れる度に冬も本格的な深まりをみせていくということでしょうか。 冬支度も少しずつでもしてい […]

2021年11月25日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 空気が乾燥して肌荒れが気になる季節です。洗い物とかするとどうしてもお湯を使ってしまうので手荒れが気になりますね。 さて、本日は不規則な食生活についてです […]

2021年11月18日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 寒くなってきて冬の野菜が楽しみになってきました。 白菜やブロッコリー、ニンジンなんかもそうでしょうか。山芋も美味しいです。新米で美味しい野菜を楽しみにしたいものです。 […]

2021年10月28日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 さて、本日のお口豆知識は、歯ブラシの選び方です。 みなさん歯ブラシはどんなものを選んでますか? ドラッグストアやスーパーなどで目についたものでしょうか、CMでよく見か […]

2021年10月20日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 秋はやはりスポーツの秋でしょうか。 高校野球の秋季関東大会の茨城県予選で我が母校がベスト4にまで勝ち上がったと新聞で知って小躍りするぐらいびっくりしました。 関東大会 […]

2021年10月14日
筑西からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 雨が降るたび晴れるたびに秋が深まっていくのが感じられます。 味覚の秋も健康な歯で楽しみたいですね。 さて、きょうはつめものかぶせものの二次むし歯についてで […]