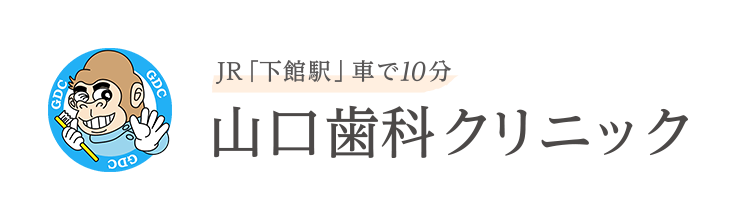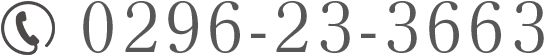2024年07月15日
睡眠不足がお口の中に??
こんにちは 山口歯科クリニックの事務長です 7月に入り、不安定なお天気や暑くて大変な日が増えました。 夜も暑くてなかなか寝付けなかったり、途中で暑くて起きてしまうこともありますね。 しばらくは睡眠不足となる […]


2024年07月15日
こんにちは 山口歯科クリニックの事務長です 7月に入り、不安定なお天気や暑くて大変な日が増えました。 夜も暑くてなかなか寝付けなかったり、途中で暑くて起きてしまうこともありますね。 しばらくは睡眠不足となる […]

2024年06月23日
こんにちは!! 当法人では、歯科医師が定期的に研修を行っています。今回のブログではその様子を一部ご紹介いたします! 歯科医師の先生方が経験した患者様とのうれしいエピソードの発表 理事長からの講義 毎日の歯科 […]

2024年04月29日
こんにちは! 医療法人G・D・C 採用担当のsae です! 本日は医療法人G・D・C の採用教育についてご紹介いたします 本年度もフレッシュな新人スタッフがたくさん入社してくれました。昨年の内定式・3月30日のオリエンテ […]

2024年04月29日
マスクを外しても好印象。新生活がはじまる前にしておきたい「お口のメンテナンス」 3月は新生活への準備が始まる大事な時期です。 別れのあとにやってくる新しい出会いや挑戦に胸を躍らせる一方で、初対面の人たちとの […]

2024年02月15日
みなさんはどんなタイミングで歯科医院に行きますか? 「痛みが出てから」「炎症が起きて腫れてから」など、何らかの症状が出てようやく歯科医院に行くという人も多いのではないでしょうか。 しかし、歯科疾患は自覚症状 […]

2023年12月24日
こんにちは。医療法人G・D・C 山口歯科クリニックのsaeです。 今日は一本の歯の大切さをお話したいと思います。たかが1本の歯。でも大きな価値のある1本です。5つの項目に分けてお話させてください。 1. **歯の健康と全 […]

2023年11月28日
年末年始の休診日についてお知らせいたします。 令和5年12月28日(木)午後~令和6年1月3日(水) が休診日となります。 1月4日(木)より通常診療致します。 皆様にはご不便お掛けいたしますが予めご了承の程お願いいたし […]

2022年04月27日
ゴールデンウィーク期間中の休診日についてお知らせいたします。 令和4年4月29日(金) 5月1日(日) 5月3日(火) 5月4日(水) 5月5日(木) が休診日となります。 5月6日(金)より通常診療致します。 皆様には […]