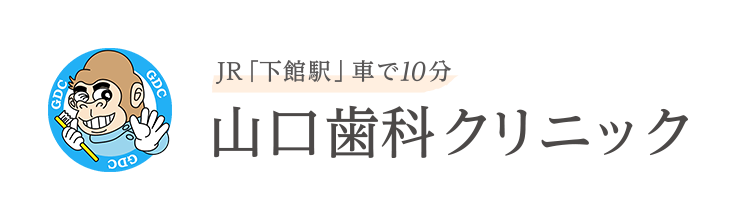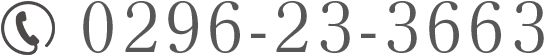2019年06月25日
休診日のお知らせ
令和元年6月26日(水)、27日(木)は研修のため休診となります。 ご不便お掛け致しますがあらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 尚、6月28日(金)より通常診療致します。 山口歯科クリニック


2019年06月25日
令和元年6月26日(水)、27日(木)は研修のため休診となります。 ご不便お掛け致しますがあらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 尚、6月28日(金)より通常診療致します。 山口歯科クリニック

2019年06月19日
梅雨の晴れ間が気持ちいいです。貴重な晴れ間でお洗濯に忙しくされてる方もいらっしゃるでしょうか。 さて、本日はお口のニオイについてです。。 自分で気になってるけどなかなか人に聞いたりできず悩まれている方もいらっしゃいますの […]

2019年06月12日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 梅雨寒の日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか? 暑い日から一転寒いぐらいになりましたので体調崩されている方もいらっしゃるかもしれませんね。体調管理に気をつけて […]

2019年06月5日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 6月になって昼が長くなったのを実感するようになりました。 夕方も7時ぐらいまでは明るくなんとなく1日を長く使えているように思えます。 梅雨入りするまでの貴重な晴れ間の […]