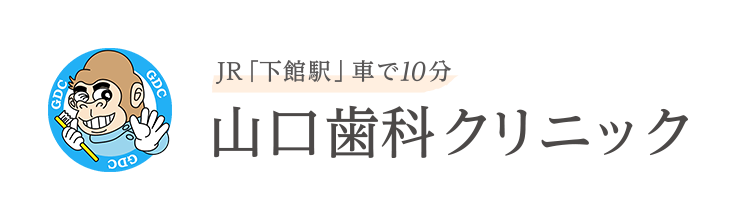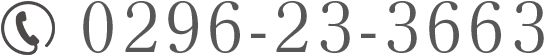2020年07月10日
噛みしめチェックしてみましょう! 〜お口豆知識
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 豪雨の影響で各地に被害が出ています。 被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。 さて、本日のお口豆知識は、「噛みしめ」についてです。 みなさんは […]


2020年07月10日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 豪雨の影響で各地に被害が出ています。 被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。 さて、本日のお口豆知識は、「噛みしめ」についてです。 みなさんは […]

2020年05月28日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 全国的に緊急事態宣言が解除され人の動きも徐々に活発になってきているようです。第二波、第三波を不正でいくためにも三密を避けて引き続き不要不急の外出は控えていきたいですね […]

2020年05月22日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 真夏のような暑さになったかと思えばこの何日かは肌寒く服装も悩ましいですね。 ご体調はいかがですか? さて、今日は入れ歯についてお話します。 入れ歯はその […]

2020年04月23日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 コロナウイルスの影響で思うように外出できずちょっと気分的にも鬱々としてしまう方も多いかと思います。 家の中でもできるような運動したり、家でもできるような楽しみをいろい […]

2020年03月25日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 コロナウイルスの影響でオリンピックが延期になるようです。経済的な面でも気になることが多くなります。 1日も早くおさまってくれることを祈るばかりです。 さ […]

2020年03月4日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 昨日のポカポカ陽気とはうって変わって冷たい雨の水曜日です。 コロナウイルスが猛威をふるっており、学校が休校になったりトイレットペーパーやティッシュが売り場からなくなっ […]

2020年02月26日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 さて、本日のお口豆知識は「喫煙と歯周病」の関係についてです。 まずはこの表を見ていただきます。 発ガン性物質やさまざまな有害物質を含んでいる煙草の煙。様 […]

2020年02月12日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 さて、今日はメタボの正しい意味について知っておいていただきたお話です。 「最近お腹が出てきちゃって、、、」と鏡を見てはため息をついてる方も多いのではないでしょうか。メ […]

2020年02月5日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 今年の冬は暖冬傾向にあるようで、当の筑西市でも積もるような降雪はまだ無いです。 立春を過ぎたとはいえこれからが寒さの本番のようですので、暖冬だからと気を緩めずに寒さ対 […]

2020年01月29日
筑西市からこんにちは、山口歯科クリニックのはまです。 新型コロナウイルスについては報道でもあるように大きく広がっているようです。 うがい手洗いやマスク等の対策をしっかりして予防していきたいですね。 さて、本 […]